今朝、Twitterを眺めていたら
明後日、東京芸術劇場で弾くラフマの2番コンチェルトの解説動画です↓https://t.co/8nqIgRX7Sv
— Kotaro Fukuma/福間洸太朗 (@KotaroFukuma) January 24, 2020
いつものようにラフマ様、精神科医のダール先生に加え、今回は特別に、私がこの曲を最初に聴いた時の演奏をされたV.アシュケナージ氏(先日引退表明された😭)に敬意を込めて演奏したいと思います!
ピアニスト福間洸太朗さんがアップされていた、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の解説動画です。
なかなかわかりやすく良いなあ、と思ったのでここでシェアさせていただきます!
そして・・今日はこのラフマニノフ作曲「ピアノ協奏曲第2番c-Moll op18について紹介します。(以前、この曲について調べて、ブログにも書いた事があったので、リライトです)
ラフマニノフ作曲・ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18
あの「のだめカンタービレ」に登場してすっかり有名になった感のあるピアノ協奏曲ですが、本当にロマンチックな曲です。
ラフマニノフが精神的にダメージを受けるまで
まずは作曲をしたラフマニノフですが、彼は1873年4月1日(ユリウス暦で3月20日) ロシア、ノヴゴロド州のセミョノヴォの生まれです。
セルゲイ・ラフマニノフの両親
父、母ともに裕福な貴族の家系の出身でしたが、セルゲイが生まれる頃には 没落。
父は ジョン・フィールドにも習ったことのある アマチュア・ピアニストで音楽の素養のある人だったそうです。ちなみに、ジョン・フィールドという人はアイルランドのピアニストで作曲家。「夜想曲」(ノクターン)を書いた、という事で有名になりました。このフィールドのノクターンが、ショパンに影響を与えました。アイルランド人なのに、ラフマニノフの父にピアノを教える??と思ったところ、どうやらフィールドは1803年にロシアに渡り、そのままロシアに住み続けたようですね。
ラフマニノフがピアノを習いはじめて、音楽院へ
彼は4歳の頃からピアノを習っていましたが、1882年の「農奴解放政策」の影響で 破産、家庭は崩壊します。
しかし、音楽の才能を認められて、ペテルブルクの音楽院に入学するのですが、あまり勤勉な学生でなかったようです。
従兄のピアニスト、アレクサンドル・ジロティの勧めで モスクワ音楽院に転入をし、ニコライ・ズヴェーレフにピアノを学んでいます。
このズヴェーレフはラフマニノフにピアノ演奏以外の事に興味を持つ事を禁止していたようですが、セルゲイは作曲に対する興味を抑えることができず、音楽院の作曲科も卒業しています。
作曲してくれて良かった〜〜ですよね。でないと、これほどの素晴らしい曲が生まれなかったかもしれないのですから。
モスクワ音楽院卒業と交響曲第1番の失敗
1892年にモスクワ音楽院を卒業。卒業制作として書かれた歌劇「アレコ」は金メダルを受賞し、チャイコフスキーにも称賛されました。このことを誇りに思ったラフマニノフは2台ピアノのための組曲第1番「幻想的絵画」をチャイコフスキーに献呈しています。
1893年、チャイコフスキーが亡くなると「悲しみの三重奏」を作曲し、この曲も好評を得ました。
1895年に「交響曲第1番」を完成させ、1897年にグラズノフの指揮でペテルブルクで初演されましたが、作曲家で音楽評論家のキュイにこき下ろされ、記録的な大失敗となってしまいます。
精神科医のダーリ博士に治療を受ける
この失敗でラフマニノフは鬱傾向と自信喪失に陥り、作曲が無理な状態となります。
そこで、この鬱状態になった作曲家を 音楽愛好家でもあった精神科医のニコライ・ダーリ(ダール)が心配し、ラフマニノフに治療を施した、と伝えられています。
1899年にロンドン・フィルハーモニック協会の招きでイギリスに渡ったラフマニノフはピアノ協奏曲の作曲の依頼を受けますが、なかなか筆のすすまないラフマニノフにダーリ博士が「あなたは素晴らしいピアノ協奏曲を書く」という催眠療法を施し、
そのおかげで ラフマニノフも自信回復し、このピアノ協奏曲第2番を完成させる事ができた、とか。現在はこのダーリ博士の催眠療法の効果については疑問視もされています。
催眠療法が本当に効果があったのか?は実際のところ、わからないですよね。本人が「助かった!」と思えばそうなのだろうし。
このピアノ協奏曲をラフマニノフは ダーリ博士に献呈してます。なので、すくなくとも本人はダーリ博士のおかげだと感じているという事ですね。
本人がそう感じたのなら、ダーリ博士の治療が効果的だった、という事なのでしょう。
ピアノ協奏曲第2番の完成
このピアノ協奏曲の第2楽章、第3楽章は 治療を受け始めてすぐの1900年夏にほぼ完成、同年12月2日に初演しています。
第1楽章を書くことには苦労をしたそうですが、それも1901年の春には完成しています。1901年11月9日(ユリウス暦10月27日)に 作曲者自身のピアノ、従兄のアレクサンドル・ジロティの指揮、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で 全曲初演し 大成功を収めています。
1楽章が、それに続く2,3楽章より後に作曲されたのですね。
ピアノ協奏曲第2番の構成
全3楽章です。
- 第1楽章 モデラート (Moderato)
- 第2楽章 アダージョ・ソステヌート (Adagio Sostenuto)
- 第3楽章 アレグロ・スケルツァンド (Allegro Scherzando)
伝統的なピアノ協奏曲のスタイルで3楽章構成、オーケストラも伝統的な2管編成です。ここに チャイコフスキーから受け継いだヨーロッパの伝統的な保守的な音楽の作法をラフマニノフが持っていることが感じとれます。
伝統的な調性で書かれたありながら(ちなみに・・ラフマニノフとスクリャービンは同世代です)息の長いメロディにどこか斬新な和声を伴い、ある意味、新鮮な音楽となっています。
・・・そう、聴いていて、全く古臭くないですよね。クラシック音楽とは関係ない内容のドラマや映画でも使われるくらい、なんだか心に感じるメロディやハーモニーが溢れているし。
ところで、あの印象的な第1楽章冒頭のピアノのソロは 「鐘」の音を表していることで有名です。(とても印象的で、子供の頃、私は手が小さいにもかかわらず、あの冒頭が弾いてみたくて、友人と「連弾」しました。いえ、連弾用に書かれていないのですが、片手で弾くべきところを両手で弾いて、友人は右手パート、私は左手パート、とかその逆とか、という感じで。自分でその音を出せるだけで嬉しかったのです!)
「鐘」は時計等なかったその昔の人々の生活には欠かせないものであり、特にロシアでは その存在感は非常に大きいものでした。
教会の礼拝の始まりの合図や 結婚式、お祭り、葬式などの合図など 生活の中になくてはならないものとなっており、「鐘」の愛称「鈴」は 魔除けでもあったと言われています。
ラフマニノフには フィギュアスケートで有名になったピアノ曲の「前奏曲 鐘」や 合唱交響曲「鐘」op35など、他にも鐘の音がモチーフになった曲があります。

ラフマニノフは ロシア革命の勃発により、その混乱を避けてロシアを離れ 二度と祖国には戻っては来ませんでした。
1918年にアメリカに渡り、ピアニストとして大活躍しましたが 作曲の方は低調になってしまいます。
なぜ作曲をしないのかと問われた際、
「どうやって作曲するというのだ。メロディがないのに。それに長い間ライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いていないんだ」
と言ったと伝えられています。
このメロディがないのに・・の中には 「鐘の音も聞こえないのに・・」という意味もあるのではないでしょうか。
おすすめのCD、音源
やはり作曲家本人の演奏は、大変興味深いです。一度は聴きたい!と思って購入しました。
ラフマニノフは手のかなり大きい人だったというのは有名で 特にこの曲の冒頭は 手が大きくないと、「鐘」のモチーフの和音が一度に掴めません。
ラフマニノフがどのようにイメージしてこの曲を書いたのか伝わって来ます。さすがに古い録音で 音は悪いですが、一度は聴いておきたい音源だと思います。
ロシア出身のアシュケナージのピアノです。福間さんが「この曲を最初に聴いた時の演奏をされたアシュケナージ」だったと述べておられますが、実は私もこの曲を最初に聴いたのがアシュケナージの演奏でした。
音がとても綺麗で、この曲の魅力が十分発揮できていると思います。おかげですぐにこの曲が好きになりました!
アシュケナージは手が小さいので最初の和音がかなりゆっくりのアルペジオになっています。ラフマニノフ本人の演奏と比べる意味でも面白いかもしれませんね。

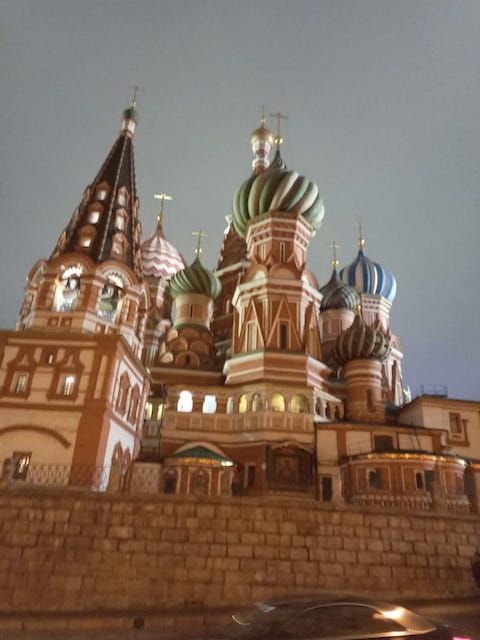


コメント